【お知らせ】
※2026年1月5日(月)9:00よりシステムが新しくなります。ユーザー登録がお済の方は、ユーザーID・パスワードがそのまま使用できます。新たに登録申請する必要はありません。
下記の[システムログイン]からお進みください。
システム操作説明会動画(2025年12月17日開催済み)
コンサルタント向け
コンサルテーション依頼者向け
★新システム:操作マニュアルを掲載いたします★
・操作マニュアル(ユーザー登録・変更用)
・操作マニュアル(コンサルタント用)
・操作マニュアル(依頼者用)
病理診断が困難な症例について、全国の病理診断医から、各臓器がんに精通する病理医へのご相談(コンサルテーション)をエキスパートとしてお受けします。 コンサルテーションのお申し込みから意見の回答まで、オンラインシステム(名称「日本病理学会・国立がん研究センター病理診断コンサルテーションシステム」)を用いて行いますので、ご利用にあたっては、以下の手順と注意事項を必ずご確認ください。
1.病理診断コンサルテーションについて
日本病理学会・国立がん研究センター がん対策研究所が提供するこの「病理診断コンサルテーション」は、病理診断に従事している病理医を支援するものです。全国の病理医の方々は、さまざまな臓器・領域のがんの病理診断に従事されていますが、日常の病理診断業務の中では、その臓器・領域の専門家でないとなかなか診断の難しい病変に少なからず遭遇します。また、それぞれの診療科から要求される病理診断の精度は日々高まり、病理診断医にも高い専門性が求められるようになってきています。そこで、各臓器がんの病理診断の経験が豊富な病理医にコンサルタントとして協力をお願いし、より診断精度の高い診断意見を提供していただき、病理診断支援を行うことが最大の目的です。
2.病理診断コンサルテーションの流れ
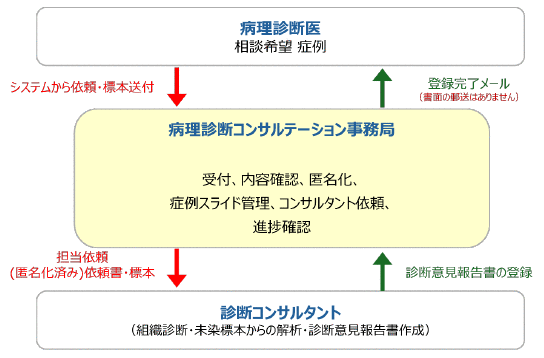
●はじめに オンラインシステムにログイン
所定のアカウントを使用してログインしてください。ユーザー登録はこちら
①症例情報の入力
必要な臨床情報・病理所見を正確に記載し、システムから診断依頼を申請してください。
②資料の提出
申請受理メールが届いたら、プレパラートや画像データなど診断に必要な資料を事務局あてに送付してください。
③専門医による診断
各臓器がんに精通したコンサルタントが意見報告を返答します。
④結果の確認
オンラインシステム上で報告書の内容を確認できます。
⑤フォローアップ情報の登録
約2ヶ月後にフォローアップ情報の登録依頼がありますので、ご協力願います。
3.利用にあたってご了解いただくこと
1)利用できる方および対象標本について
■利用対象者
- 病理診断コンサルテーションの依頼対象者は、病理診断に従事する病理診断医です(ただし、民間検査会社等、営利団体の所属者を除く)。臨床医、患者さんご本人やご家族などからの直接のご依頼はお受けできません。
■対象となる症例
- 病理診断の確定が難しいと考えられる症例(生検標本・手術標本の組織診断)や専門家に意見を求めたい症例。
■費用について
- 手数料は原則無料です。標本送付にかかる実費のみご負担いただきます。
- コンサルタントが必要と判断し、特殊補助解析(IHC, FISH, 遺伝子解析)を行う場合:
◇国立がん研究センターで施行した場合は無料です。
◇一部のコンサルタント(特任コンサルタント)が自施設で行った場合は有料となる場合がありますので、詳しくは病理学会ホームページをご覧ください。
■対象外のコンサルテーション
以下の目的による依頼は受け付けておりません。
- 特定の免疫染色、FISHや遺伝子解析を目的とした依頼
※これらは、コンサルタントが診断に必要と判断した場合に実施されます。 - 剖検の全体診断(腫瘍の組織診断を除く)
- 医療過誤および裁判係争中の症例
2)個人情報保護について(重要)
- 患者の特定につながる情報(氏名、イニシャル、患者ID、二次元コードなど)は依頼書、その他添付資料に記載しないでください。病理診断に重要と考えられる情報(居住地、職業等)を登録する場合も、個人が特定されないよう配慮してください。プレパラートには、依頼書と照合可能な病理標本番号を鉛筆で記載してください。
- マクロ画像・臓器切り出しの写真・放射線画像などをCD-R等で提出する際は、必ず匿名化してください。匿名化が不十分な場合でも、事務局側で匿名化が不可能なものにつきましては、そのままコンサルタントにお送りします。誤配等による個人情報流出について、事務局では責任を負いかねます。
- 事務局が受け付けた症例には、独自の受付番号(CIS番号)を発行します。コンサルタントには、個人情報を除いた資料とCIS番号のみが伝達されます(匿名化)。したがって、診断意見報告書はCIS番号に基づいて作成されます。
3)コンサルタントについて
コンサルタントとして、一定の基準に基づく各臓器・領域のがん病理診断の専門家に協力をお願いしています。
詳しくはコンサルタント一覧をご覧ください。
- 事務局が、症例に最適なコンサルタントを選定します。
- 特に指名希望がある場合は、システムの[コンサルタント希望有無]欄からご指名ください。ご希望に添えるよう努力いたします。
※診断に必要な情報提供のため、コンサルタントから依頼者へ直接連絡(メール・電話)をする場合がありますのでご協力ください。
4)診断意見報告書について
提供される診断意見報告書は、依頼施設における病理診断報告書作成過程での参考資料です。診療記録としての正式な病理診断報告書ではありません。最終的な診断責任は、依頼者にあります。
5)フォローアップ情報の登録について
診断意見報告書が登録された後、約2ヶ月後を目安にフォローアップ情報の登録依頼メールが届きます。
ご登録された情報は、コンサルタントへのフィードバックとして活用されます。
登録期限は特に設けておりませんので、適宜適切な時期にご登録ください。
6)一般的な注意事項
- 診断の最終責任は依頼者にあることに留意してください。
- 依頼が特定の臓器に依頼が集中する傾向があり、時間と労力などを犠牲にして協力いただいているコンサルタントにとって、過度の負担とならぬよう、的確な診断依頼の登録と標本の送付を心がけてください。また、所見の記載不備・臨床情報の再確認作業などが生じないようご配慮願います。
- コンサルタントからの診断意見報告までは、コンサルタントの手元に標本到着後およそ3~4週間前後を要するものと予想されますが、内容の難易度や 付随検査の必要性に応じて前後します。 標本の送付状況などはシステムで確認できるほか、コンサルタントに標本が渡った後の進捗状況については事務局でも確認します。連絡などがないまま1ヶ月以上を経過する場合には事務局にお問い合わせください。多数の標本が集中するなどの繁忙時には、数日程度の遅延が生じる可能性があります。
- その他のご不明点は、事務局までご連絡ください。
7)情報の取り扱いについて
- 本システムを通じて得られた病理診断情報は、日本病理学会もしくは国立がん研究センターが所管する研究や教育等事業に使用される可能性があります。
- コンサルタントが実施した種々の染色や遺伝子解析等のガラス標本や生データは、原則として返却や提供を致しません。
4.ユーザー登録および情報変更について
病理診断コンサルテーションシステムを利用するには事前のユーザー登録が必要です。
以下のリンクにアクセスして、【新規ユーザー登録はこちら】をクリック、必要事項を登録し【ユーザー申請】ボタンを押してください。
https://pathology-consultation.ncc.go.jp/pcs/login
ご自身のメールアドレスは、所属施設で付与されたものをご申請ください(GmailやYahoo mail等のフリーメールアドレスは、セキュリティの都合上、また迷惑メールフォルダ等に入る可能性も多く推奨していません)。
申請内容は事務局で確認後、数日以内に登録されたメールアドレス宛にアクティベーションコードを送信します。メールの案内に従ってコードを入力し、登録を有効化してください。
なお、1人につき1つのアカウント登録となります。同施設で複数名が登録される場合は、人数分のアカウントが必要です。
また、登録情報に変更が生じた場合、所属施設の異動を伴わない変更は、システムにログインし【マイページ】からご自身で修正可能です。異動など所属施設が変わる場合は、お手数ではございますが、下記項目を入力いただき、メールにて事務局にお知らせください。
※所属施設が一覧に存在しない場合も事務局にて施設を追加しますのでメールにてご連絡ください。
【ユーザー情報変更申請】
-----------------
宛先:pathconsult@ml.res.ncc.go.jp
件名:病理診断コンサルテーション ユーザー情報変更申請
※旧施設名:
※旧メールアドレス:
氏 名(漢字):
ふりがな(かな):
メールアドレス:
施 設 名:
部 署 名:
役 職:
郵 便 番 号:
住所(都道府県から):
連絡先電話番号:
連絡先内線番号:
----------------
5.コンサルテーションの依頼方法
コンサルテーションの依頼は、下記に留意して依頼症例の詳細を記入してください。
依頼にはユーザー登録を用いて病理診断システムへのログインが必要ですので、未登録の方は上記「4.ユーザー登録および情報変更について」をご参照ください。
1)診断依頼登録
以下のシステム専用サイトにアクセスし、ユーザーIDとパスワードを用いてログインしてください。
URL: https://pathology-consultation.ncc.go.jp/pcs/login
- [新規診断依頼]の[作成する]ボタンをクリックし、診断依頼登録画面で依頼目的を含む必須事項を漏れなく入力してください。希望するコンサルタント(一覧表参照 )があれば、「コンサルタント希望有無」の項目で該当するコンサルタントの氏名を選択してください(希望がなければ事務局が割り当てます)。※特任コンサルタントを希望される場合、有料となることがあります。
- 国立がん研究センターではがん診療の支援が目的となっているため、非腫瘍性疾患が検討対象の場合は診断依頼画面の[疾患区分]の項目で「非腫瘍性疾患」を選択してください。その場合の取り扱いは日本病理学会での対応となります。
- 病理診断に必須である十分な臨床情報や画像情報を記載してください。また免疫染色などの重複した検討を減らし、迅速な診断意見報告書の作成のため、病理学的な検索状況等も出来るだけ詳しく記載ください。
- 診断依頼には患者の特定につながる患者氏名、イニシャル、患者ID、二次元コードなどは入力せず、標本番号(送付プレパラートと照合可能な番号であること)のみを記載してください。
- 入力方法の詳細については操作マニュアルをご参照ください。「診断依頼を申請する」→「OK」ボタンを押すことで症例情報の登録は完了です。
- 登録された情報を基に指名されたコンサルタントの候補者に依頼が通知され、その受諾をもって担当コンサルタントが確定します。なお、入力いただいた内容に不備などがあった場合には,後で事務局から加筆・修正等を依頼させていただくことがあります。
2)送付資料について
A. プレパラートもしくはバーチャルスライド画像
コンサルテーションを受けたい標本につき、(1)(2)両方をご用意ください。
(1)HE染色標本2枚* (1枚:コンサルタント用、1枚:事務局管理用**)
(2)免疫染色用の未染標本15枚
(シランコート等の組織剥離防止処置を施したスライドグラスで作製されたもの)
*バーチャルスライド画像のみの診断もお受けいたしますが、症例によっては標本を送付いただく場合があります。
**HE染色標本を数種類お送りいただく際、事務局管理用のHE染色標本はメインの切片1枚のみで結構です。
B.依頼書に付帯する臨床資料
依頼者は、診断の参考となる肉眼写真、X線写真、電顕写真などを可能な範囲でご準備ください。これらの資料は、診断依頼登録画面でファイルをアップロードするか、印刷物やCD-R等のメディアに保存して標本とともに送付してください。特に骨腫瘍の場合にはX線写真、CT、MRIなどの画像が必須です。
また、送付いただいた資料は原則として返却できませんので、必要に応じて複製を取っておいてください。
すべての送付資料において、患者の特定につながる情報(氏名、イニシャル、患者ID、施設標本番号、二次元コードなど)を記載しないでください。
X線フィルム、CT、MRIなどの画像に記載されている氏名、患者IDなどの個人情報も削除してください。
病理診断に重要と考えられる情報(居住地、職業等)を用紙に記載する場合でも、患者の特定につながらないようにご配慮願います。
- 送付いただいたプレパラートは、残余未染標本も含めて最終的にはコンサルタントの手元に保管されます。
(未染標本が用意できない場合は、事務局へご相談ください。) - 送付に際し、プレパラートが破損しないようケースや緩衝材などを利用して荷造りするなど十分注意してください。
また封筒の破損、標本とケースあるいは標本同士の粘着も多く見受けられるので注意してください。 - 患者の特定につながる患者氏名やイニシャル、カルテ番号、二次元コードなどは記載せず、標本番号(依頼書記載と照合可能な番号であること)のみを鉛筆でプレパラートに記載してください。患者氏名が印字されている場合は有機溶剤対応のペンで消すか、削り取ってください。
- 依頼元で施行された免疫染色標本等の返却希望の標本がある場合、レターパック、着払いや送料相当の切手を同封するなど返却費用は依頼者に負担していただいています(コンサルタントの施行した免疫染色等の資料は返送しません)。
また、返却希望標本は、ケースを分けるなど返却不要標本と混同しないようにしてください。
C. 送付用ラベルおよび送付先(腫瘍・非腫瘍ともに)
上記A・B2つの資料を下記の「病理診断コンサルテーション事務局」まで郵送してください。その際、レターパックや書留(簡易書留可)・ゆうパック・各種宅配便など配達の確認や追跡が可能な方法で送付ください。また、標本の取り違えを防止するため、診断依頼画面にある【送付用ラベルを印刷する】ボタンを押し、プリントアウトしたラベルを貼ってください。貼れない場合は、封筒や配送伝票にCIS番号をご記入願います。(ラベルを印刷することで、発送ステータスが進んでいきます。)
資料送付先(病理診断コンサルテーション事務局)
病理診断コンサルテーション事務局
〒104-0045 東京都中央区築地 5−1−1 国立がん研究センター
がん対策研究所 がん医療支援部
病理診断支援推進室 病理診断コンサルテーション事務局
Email:pathconsult@ml.res.ncc.go.jp
電 話:03−3547−5201(内線 1702)
D. 標本の追跡について(依頼者-事務局-コンサルタント)
依頼者から事務局、事務局からコンサルタントまでの標本の輸送状況をシステム上でも確認することができます。詳しくはマニュアルを参照ください。
6.意見報告書の閲覧について
- コンサルテーションを受諾したコンサルタントが標本・資料を受領した後、システムに診断意見を入力して報告書が登録されると、依頼者にメールで「診断意見報告書登録完了通知」が配信されますので、システムにログインして「診断意見報告書」の内容をご確認ください。
- 通知メールにシステムへのリンクが記載されていますので、そのリンクからでも[診断意見報告書]を閲覧することが可能です。
- 事務局からのメールが確実に受信できることを、「診断依頼情報登録完了のお知らせ」メール等で確認ください。
7.学術研究資料として使用する際の注意事項
本コンサルテーションに申し込まれた症例の学会・論文発表等の学術的利用については、依頼者にその優先権があります。
- 依頼者がコンサルテーションにより得た意見や情報を学会・論文等で報告する場合には、あらかじめ担当コンサルタントにその旨を連絡していただくとともに、必要に応じて共著者に加える、謝辞を述べるなどの謝意を示してください。また、当方事務局にも事前にご連絡ください。
- コンサルタントが依頼症例を学術研究資料として使用する際には、依頼者の同意のほか、患者の同意を含め各診療施設の倫理規定を順守することが必要です。当方事務局にも事前にご連絡ください。
※コンサルタントが実施した免疫・特殊染色と FISH のガラス標本は原則として返却いたしません。
8.FAQ
臨床医など病理医以外の場合は依頼症例を担当した病理医を通してご依頼ください。
9.お問い合わせ先
-
腫瘍性疾患について(国立がん研究センター)
病理診断コンサルテーション事務局
前田、松尾
〒104-0045 東京都中央区築地 5−1−1
国立がん研究センター がん対策研究所がん医療支援部
病理診断支援推進室
Email:pathconsult@ ml.res.ncc.go.jp
電話:03−3547−5201(内線 1702) -
非腫瘍性疾患について(日本病理学会)
日本病理学会事務局
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-17
神田 IN ビル 6 階
Email: jsp-consult@ pathology.or.jp
電話:03-6206-9070
FAX:03-6206-9077
10.病理診断コンサルテーション コンサルタント一覧
(2025年12月1日現在)
| 相島 慎一 | 九州大学大学院 構造病態病理学教室 |
|---|---|
| 秋葉 純 | 久留米大学医学部 病理学講座 |
| 浅野 直子 | 長野県立信州医療センター 遺伝子検査科 |
| 新井 冨生 | 東京都健康長寿医療センター 病理診断科 |
| 安齋 眞一 | PCL 東京病理/細胞診センター 病理診断部 |
| 池田 善彦* | 国立循環器病研究センター 病理部 |
| 石井 源一郎 | 国立がん研究センター 先端医療開発センター 臨床腫瘍病理分野 |
| 石川 雄一 | 公益財団法人佐々木研究所附属 佐々木研究所 |
| 石澤 圭介* | 東京都立神経病院 検査科 |
| 石津 明洋* | 北海道大学大学院 保健科学研究院 |
| 泉 美貴 | 昭和医科大学医学部 医学教育学講座 |
| 市原 周 | 名古屋医療センター 病理診断科 |
| 伊東 慶悟 | 日本医科大学 武蔵小杉病院 皮膚科 |
| 井内 康輝 | ひろしま病理診断クリニック |
| 井上 健 | 大阪市立総合医療センター 病理診断科 |
| 井野元 智恵 | 東海大学医学部付属八王子病院 病理診断科 |
| 入江 太朗 | 岩手医科大学 病理学講座病態解析学分野 |
| 岩淵 英人 | 静岡県立こども病院 病理診断科 |
| 植田 初江* | 北摂総合病院 病理診断科 |
| 牛久 哲男 | 東京大学大学院 医学系研究科 人体病理学・病理診断学 |
| 宇月 美和* | 福島県立医科大学 保健科学部・臨床検査学科 |
| 浦野 誠 | 藤田医科大学ばんたね病院 病理診断科 |
| 江中 牧子 | 藤沢市民病院 病理診断科 |
| 大池 信之 | 聖マリアンナ医科大学 病理学 分子病理 |
| 大石 直輝 | 山梨大学医学部附属病院 病理診断科 |
| 大江 知里 | 兵庫医科大学医学部 病理学講座 病理診断部門 |
| 大喜多 肇 | 国立がん研究センター研究所 中央病院 病理診断科 |
| 大橋 健一 | 東京科学大学 大学院医歯学研究科 人体病理学分野 |
| 大橋 瑠子 | 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 分子・診断病理学分野 |
| 岡 輝明 | (公財)結核予防会 複十字病院 病理診断部 |
| 長村 義之 | 日本鋼管病院 病理診断科 |
| 尾島 英知 | 栃木県立がんセンター分子病理分野兼統括診療部病理診断科 |
| 小田 義直 | 九州大学大学院医学研究院 形態機能病理学 |
| 小幡 博人 | 埼玉医科大学総合医療センター 眼科 |
| 海崎 泰治 | 福井県立病院 病理診断科 |
| 覚道 健一 | 和泉市立総合医療センター 病理診断科/甲状腺疾患センター |
| 加瀬 諭 | 奈良県立医科大学 眼科学講座 |
| 加藤 生真 | 静岡県立静岡がんセンター 病理診断科 |
| 加藤 省一 | 佐賀大学医学部 病因病態科学講座診断病理学分野 |
| 加藤 良平 | 伊藤病院 病理診断科 |
| 門田 球一 | 香川大学医学部 分子腫瘍病理学 |
| 亀山 香織 | 昭和医科大学横浜市北部病院 臨床病理診断科 |
| 茅野 秀一 | 埼玉医科大学 保健医療学部臨床検査学科 |
| 加留部 謙之輔 | 名古屋大学医学系研究科 臓器病態診断学 |
| 川井田 みほ | 伊藤病院 病理診断科 |
| 川崎 朋範 | 埼玉医科大学国際医療センター 病理診断科 |
| 河内 洋 | 公益財団法人がん研究会 がん研究所 病理部 |
| 川本 雅司* | 湘南藤沢徳洲会病院 病理診断科 |
| 神澤 真紀 | 神戸市立西神戸医療センター 病理診断科 |
| 岸川 さつき | 国立がん研究センター研究所 中央病院 病理診断科 |
| 木谷 匡志 | 国立病院機構 東京病院 臨床検査科 |
| 清川 貴子 | 東京慈恵会医科大学 病理学講座・同附属病院病理部 |
| 清島 保 | 九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔病理学分野 |
| 九嶋 亮治 | 滋賀医科大学 臨床検査医学講座 |
| 黒瀬 顕 | 弘前大学大学院医学研究科 病理診断学講座 |
| 桑田 健 | 国立がん研究センター東病院 病理科・臨床検査科 |
| 孝橋 賢一 | 大阪公立大学 大学院医学研究科 診断病理・病理病態学 |
| 古賀 佳織 | 福岡大学病院 病理部・病理診断科 |
| 小島 史好 | 和歌山県立医科大学 人体病理学 病理診断科 |
| 小嶋 基寛 | 京都府立医科大学 臨床病理学 |
| 後藤 明輝 | 秋田大学大学院医学系研究科 器官病態学 |
| 後藤 啓介 | 地方独立行政法人 大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 病理・細胞診断科 |
| 小西 英一 | 京都済生会病院 病理診断科 |
| 近藤 哲夫 | 国立大学法人山梨大学 医学部人体病理学 |
| 笹島 ゆう子 | 帝京大学医学部 病理学講座 |
| 笹野 公伸 | 東北大学大学院医学系研究科 病理診断学分野 |
| 佐藤 啓 | 名古屋大学医学部附属病院 病理部 |
| 佐藤 勇一郎 | 宮崎大学医学部病理学講座 腫瘍形態病態学分野 |
| 里見 介史 | 杏林大学 医学部病理学教室 |
| 塩沢 英輔 | 昭和医科大学 医学部 臨床病理診断学講座 |
| 潮見 隆之 | 国際医療福祉大学成田病院 病理診断科 |
| 柴原 純二 | 杏林大学 医学部病理学教室 |
| 澁谷 和俊* | 東邦大学医学部 真菌感染病態解析・制御学講座 |
| 清水 章* | 日本医科大学 解析人体病理学 |
| 下田 将之 | 東京慈恵会医科大学 病理学講座 |
| 城 謙輔* | 東京慈恵会医科大学 病理学講座 |
| 杉田 真太朗 | 函館五稜郭病院 病理診断科 |
| 杉野 弘和 | 北海道大学大学院医学研究科 病理学講座 腫瘍病理学分野 |
| 鈴木 忠樹* | 国立感染症研究所 感染病理部 |
| 鈴木 理樹 | 東京大学医学部附属病院 病理部 |
| 関根 茂樹 | 慶應義塾大学医学部 病理学教室 |
| 高橋 啓* | 東邦大学医療センター大橋病院 病理診断科 |
| 鷹橋 浩幸 | 東京慈恵会医科大学 病理学講座 |
| 竹内 真 | 大阪母子医療センター 病理診断科 |
| 竹下 盛重 | 済生会八幡総合病院 病理診断科 |
| 武島 幸男 | 広島大学大学院医歯薬保健研究科 病理学研究室 |
| 田中 伸哉 | 北海道大学大学院医学研究科 病理学講座 腫瘍病理学分野 |
| 田中 祐吉 | 神奈川県立こども医療センター 臨床研究所 |
| 谷口 浩和 | 帝京大学医学部 病理学講座 |
| 谷野 美智枝 | 旭川医科大学病院 病理部・病理診断科 |
| 津田 均 | 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター 病理診断科 |
| 都築 豊徳 | 愛知医科大学医学部 病理診断科 |
| 堤 寛* | つつみ病理診断科クリニック |
| 土居 正知* | 聖マリアンナ医科大学 病理学 |
| 豊澤 悟 | 大阪大学大学院 歯学研究科・顎顔面口腔病理学講座 |
| 長尾 俊孝 | 東京医科大学 人体病理学分野 |
| 中黒 匡人 | 名古屋大学医学部附属病院 病理部 |
| 長坂 徹郎 | あいち病理診断クリニック |
| 中澤 温子 | 埼玉県立小児医療センター 臨床研究部 |
| 中島 正洋 | 長崎大学原爆後障害医療研究所 腫瘍・診断病理学分野 |
| 中嶋 安彬 | 関西医科大学綜合医療センター 病理部 |
| 長嶋 洋治 | 東京女子医科大学病院 病理診断科 |
| 名方 保夫 | (株)日本医学臨床検査研究所 病理・細胞診検査課 |
| 中谷 行雄 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 |
| 中沼 安二 | 福井県済生会病院 病理診断科 |
| 中峯 寛和 | 日本バプテスト病院 中央検査部 |
| 西田 陽登 | 大分大学医学部 診断病理学講座 |
| 二村 聡 | 福岡大学筑紫病院 病理部 |
| 野島 孝之 | シーピーエル病理診断科クリニック |
| 信澤 純人 | 群馬大学大学院 医学系研究科病態病理学 |
| 羽尾 裕之* | 日本大学医学部 病態病理学系人体病理学分野 |
| 羽賀 博典 | 京都大学大学院医学研究科・医学部 病理診断学 |
| 長谷川 博雅 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 臨床検査部 |
| 長谷部 孝裕 | 埼玉医科大学国際医療センター 病理診断科 |
| 濵﨑 慎 | 福岡大学医学部 病理学講座 |
| 林 大久生 | 順天堂大学 医学部人体病態学講座 |
| 林 博之 | 原三信病院 病理診断科 |
| 原田 憲一 | 金沢大学 医薬保健研究域医学系 人体病理 |
| 久岡 正典 | 産業医科大学医学部 第1病理学 |
| 比島 恒和 | がん・感染症センター都立駒込病院 病理科 |
| 平岡 伸介 | 国立がん研究センター研究所 中央病院 病理診断科 |
| 平木 翼 | 静岡県立静岡がんセンター 病理診断科 |
| 廣川 満良 | 隈病院 病理診断科 |
| 廣島 健三 | 東京女子医科大学八千代医療センター 病理診断科 |
| 福岡 順也* | 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 情報病理学 |
| 福嶋 敬宜 | 自治医科大学医学部 病理診断部 |
| 福島 万奈 | 福井大学医学部 病理学 |
| 福永 眞治 | 新百合ヶ丘総合病院 病理診断科 |
| 藤井 誠志 | 横浜市立大学大学院 医学研究科・医学部 分子病理学 |
| 藤本 正数 | 京都大学医学部附属病院 病理診断科 |
| 古里 文吾 | |
| 堀井 理絵 | 聖マリアンナ医科大学 病理学(診断病理学分野) |
| 本間 琢 | 埼玉医科大学国際医療センター 病理診断科 |
| 牧瀬 尚大 | 千葉県がんセンター 臨床病理部 |
| 増井 憲太 | 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 |
| 増田 しのぶ | 日本大学医学部 病態病理学系病理学分野 |
| 松岡 健太郎 | 東京都立小児総合医療センター 病理診断科 |
| 松野 吉宏 | 北海道がんセンター 病理診断科 |
| 松原 大祐 | 筑波大学 医学医療系 診断病理学分野 |
| 松本 俊治 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 病理診断科 |
| 松山 篤二 | 福岡和白病院病 理診断科 |
| 真鍋 俊明 | 堺町御池病理診断科クリニック |
| 三浦 圭子 | 東京科学大学病院 病理部 |
| 三上 芳喜 | 熊本大学医学部附属病院 病理部 |
| 三木 康生* | 弘前大学大学院医学研究科 脳神経病理学講座 |
| 湊 宏 | 石川県立中央病院 病理診断科 |
| 南口 早智子 | 藤田医科大学医学部 病理診断学講座 |
| 三室 マヤ* | 三重大学医学部附属病院 病理部 |
| 宮居 弘輔 | 防衛医科大学校病院 検査部 |
| 三好 寛明 | 久留米大学医学部医学科 病理学講座 |
| 村田 普一 | 和歌山県立医科大学 人体病理学教室/病理診断科 |
| 元井 亨 | がん・感染症センター都立駒込病院 病理科 |
| 元井 紀子 | 埼玉県立がんセンター 病理診断科 |
| 森 泰昌 | 国立がん研究センター研究所 中央病院 病理診断科 |
| 森谷 鈴子 | 滋賀医科大学医学部附属病院 病理診断科 |
| 森谷 卓也 | 川崎医科大学 病理学 |
| 八尾 隆史 | 順天堂大学医学部 人体病理病態学 |
| 安田 政実 | 埼玉医科大学国際医療センター 病理診断科 |
| 谷田部 恭 | 国立がん研究センター中央病院 病理診断科 |
| 柳井 広之 | 岡山大学病院 病理診断科 |
| 柳澤 昭夫 | 京都第一赤十字病院 病理診断科 |
| 山口 岳彦 | 獨協医科大学日光医療センター 病理診断科 |
| 山口 倫 | 長崎大学病院 病理診断科・病理部 |
| 山崎 有人 | 東北大学病院 病理部 |
| 山下 篤 | 宮崎大学医学部 病理学講座 構造機能病態学分野 |
| 山下 享子 | 公益財団法人がん研究会 有明病院 病理部 |
| 山田 洋介 | 東京大学 大学院医学系研究科 病因・病理学専攻 病理学講座 分子病理学分野 |
| 山元 英崇 | 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 病理学(腫瘍病理) |
| 横尾 英明 | 群馬大学大学院 医学系研究科 病態病理学分野 |
| 吉澤 明彦 | 奈良県立医科大学 病理診断学講座 |
| 吉田 朗彦 | 国立がん研究センター中央病院 病理診断科 |
| 吉田 裕 | 国立がん研究センター中央病院 病理診断科 |
| 吉田 正行 | 国立がん研究センター中央病院 病理診断科 |
| 吉野 正 | 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病理学 |
| 渡邊 麗子 | 札幌医科大学 病理診断学講座 |
*:非腫瘍症例のみを専門としており、日本病理学会の管轄となります。
