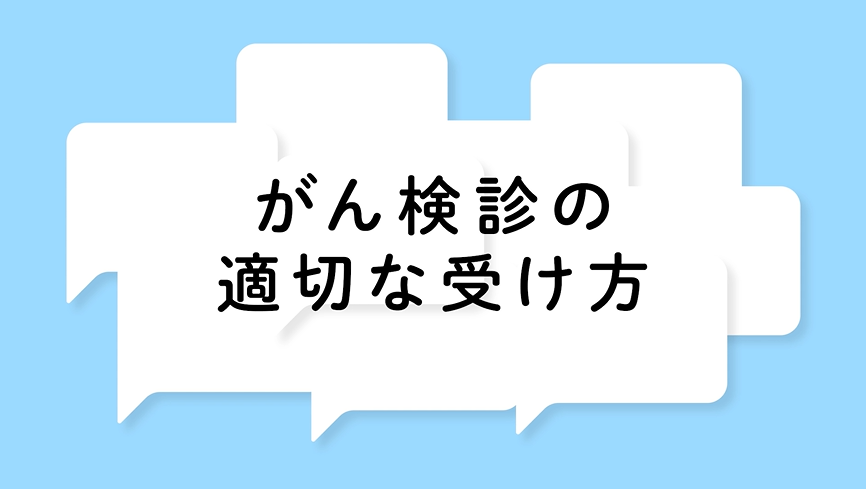1.肺がん検診とがん予防
肺がんはわが国のがんによる死亡原因の上位に位置しており、罹患する人(かかる人)は40歳代から増加します。
検診で早期に発見して治療することにより、肺がんで亡くなることを防ぐことができます。検診は自覚症状がないうちに受けることが大事です。早期の肺がんは自覚症状がありません。
血痰、長引く咳、胸痛、声のかれ、息切れなどの症状がある場合には検診ではなく、すぐに医療機関を受診してください。
現在肺がんで治療中の方は、治療終了後に、いつ検診を再開するかを主治医とご相談ください。またその他の肺の疾患で治療中の方は、がん検診を受診するかどうかを主治医とご相談ください。
日本人でたばこを吸う人は、吸わない人に比べて、男性で約4倍、女性では約3倍肺がんになりやすく、たばこを吸う年数、喫煙を始めた年齢が若く喫煙量が多いほど、そのリスクが高くなります。また、受動喫煙(周囲に流れるたばこの煙を吸うこと)も肺がんのリスクを約2~3割高めます。禁煙によってご自身と周りの人の健康な肺を守りましょう。
2.肺がん検診の方法
1)対象年齢と受診間隔
40歳から、1年に1度定期的に受診してください。
検診の利益(肺がんで亡くなることを防ぐ)と、不利益(偽陰性、偽陽性、過剰診断、偶発症など)のバランスの観点から、上記の対象年齢と受診間隔を守って、以下の「2)検診項目」にある検査を定期的に受けることが大事です。
2)検診項目
(1)胸部X線検査
- 胸のX線撮影を行う検査です。胸部全体を写すため、大きく息を吸い込んでしばらく止めて撮影します。
- 胸部X線検査の放射線被ばくによる健康被害はほとんどないとされています。
(2)喀痰細胞診(胸部X検査との組み合わせ)
- たばこを自分でたくさん吸う人に対して、喫煙との関連が大きいがんを見つけるために行う、痰に含まれる細胞の検査です。3日間起床時に痰をとり、専用の容器に入れて提出します。
- 対象は、50歳以上のご本人がたばこを吸う方で、喫煙指数(1日の喫煙本数✕喫煙年数)が600以上の方です。現在喫煙されている方だけではなく、過去に喫煙していた方も対象になります。加熱式たばこについては「カートリッジの本数」を「喫煙本数」としてカウントしてください。
- 以上の条件に当てはまらない方には喀痰細胞診は効果がありませんので、胸部X線検査のみ受診してください。
3.肺がん検診の判定後の流れと精密検査
1)検診の判定
(1)がんの疑いなし(精密検査不要)と判定された場合
「がんの疑いなし(精検不要)」と判定された場合、次回(1年後)のがん検診を受けてください。血痰、長引く咳、胸痛、声のかれ、息切れなどの症状があらわれた場合は、次回の検診を待つのではなく、すぐに医療機関を受診しましょう。
(2)がんの疑いあり(要精密検査)と判定された場合
「がんの疑いあり(要精検)」と判定された場合には、必ず精密検査を受けてください。肺がんがあっても症状が出ないことがよくあります。「次回の検診まで待とう」、「症状がないから大丈夫」などと自己判断せず、必ず精密検査を受けてください。
2)精密検査の方法
一般的な精密検査は胸部CT検査、および一部の方には気管支鏡検査です。
喀痰細胞診で要精検となった場合は、痰の検査だけをもう一度受けるのではなく、必ず精密検査を受けてください。
(1)胸部CT検査
X線を使って、肺全体の断面図を撮影し詳しく調べます。
(2)気管支鏡検査
気管支鏡を口や鼻から気管支に挿入して、病変が疑われた部分を直接観察します。必要に応じて組織を採取し、悪性かどうか診断します。
こちらのちらしでは、働く世代の方に向けて、各がん検診について知っていただきたいポイントを、コンパクトにまとめています。
こちらのちらしと動画では、働く世代の方に向けて、適切ながん検診の受け方とその内容について解説しています。
作成協力
こちらのページは、国立がん研究センター研究開発費「働く世代におけるがん検診の適切な情報提供に関する研究(2021-A-22)」の研究成果を基に作成されました。
| 2024年09月20日 | ちらし「子宮頸がん検診(HPV検査単独法)」を掲載しました。 |
| 2024年04月01日 | ちらし「子宮頸がん検診」「がん検診の適切な受け方」を更新しました。 |
| 2023年12月25日 | 内容を更新しました。 |
| 2023年03月29日 | 「2.科学的根拠に基づく肺がん検診」を更新しました。 |
| 2019年09月02日 | 「がん検診について」から「肺がん検診」の内容を分割し、更新しました。 |
| 2016年04月08日 | 「がん検診について」の「5.がん検診の効果とは?」「6.部位別がん検診の実際」について、厚生労働省の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成28年 一部改正)」に従って、更新しました。 |
| 2011年08月03日 | 「がん検診について」(肺がん検診の項目含む)を更新しました。 |
| 2006年10月01日 | 「がん検診について」(肺がん検診の項目含む)を掲載しました。 |