妊孕性とは「妊娠するための力」のことで、妊孕性温存とは「妊娠するための力を保つこと」をいいます。
がんそのものやがんの治療が生殖機能に影響すると、妊孕性が失われることがあります。妊孕性温存を検討する場合は主治医に相談しましょう。その上で、妊孕性温存が可能なのか、安全性や有効性についてもよく聞いて、患者とパートナー、ご家族とよく話し合い、慎重に検討しましょう。また、患者が小児である場合には、親の同意とともに患者本人の同意も得ることが必要ですので、主治医から年齢に応じた説明をしてもらいましょう。
こちらのページでは、がんの治療による生殖機能への影響を治療別に解説しています。また、妊孕性を温存するための方法やがんの治療後に妊娠を試みる際の方法、それらにかかる費用や助成制度についても紹介しています。妊孕性の温存を検討する場合は「4.妊孕性温存について相談したいときは」の項目を参考にお問い合わせください。
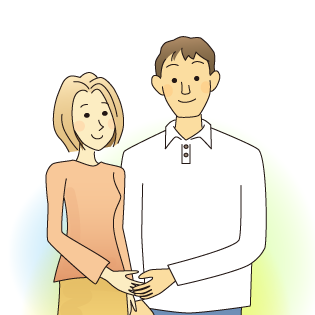
1.がんの治療による生殖機能への影響
生殖機能とは、性欲や精子の形成、勃起、射精などの機能を含めた、生殖に必要な機能のことをいいます。がんの治療が生殖機能に影響することによって男性不妊になる場合には、一時的な場合と永久的な場合があります。また、病状やがんの種類、どのような治療を行うかなどにより異なるため、主治医に十分な説明を受ける必要があります。
また、生殖器のがんだけではなく、生殖器以外のがんの治療を行った場合も、生殖機能に影響することがあります。治療ごとの生殖機能への影響については、以下の1)手術(外科治療)による影響、2)放射線治療による影響、3)薬物療法による影響の項目で説明しています。
1)手術(外科治療)による影響
手術の範囲が生殖機能に関わる器官に及ぶと影響することがあります。
| 両側の精巣を摘出した場合 | 精子を形成することができなくなります。 |
|---|---|
| 片側の精巣を摘出した場合 | 残った精巣が機能するため、妊孕性は保たれます。 |
| 膀胱や前立腺を摘出した場合 | 勃起や射精に関わる神経を損傷することで射精ができなくなります。 |
| 骨盤内にある臓器を手術した場合 | 骨盤内臓(直腸、膀胱、前立腺)に分布している、勃起や射精に関わる神経を損傷することがあり、障害が生じることがあります。 |
| 脳の視床下部や下垂体にある腫瘍を摘出した場合 | 視床下部や下垂体は精子の形成を促すホルモンの分泌に関わっているため、精子の形成に影響することがあります。 |
2)放射線治療による影響
腹部・骨盤部に照射した場合は、分裂が盛んな精子のもととなる細胞が影響を受けます。照射される放射線の量が増えるほど精巣へのダメージは大きくなり、精子を形成できなくなることがあります。
なお、放射線治療後にパートナーが妊娠しても、放射線による胎児への影響はありません。病状やほかの治療の必要性を考えた上で、特に問題がなければ治療後に避妊する必要はありません。
| 精巣へ照射した場合 | 精子の数を減らすため、精液の中に精子が少ない状態(乏精子症)や精子がない状態(無精子症)になることがあります。治療終了から数年後に精子形成が回復することもありますが、照射される放射線の量が多いと回復が難しくなります。 |
|---|---|
| 脳の視床下部や下垂体へ照射した場合 | 視床下部や下垂体は精子の形成を促すホルモンの分泌に関わっているため、精子の形成に影響することがあります。 |
3)薬物療法による影響
薬剤の中には、精子や精巣の機能に大きく影響するものと、ほとんど影響しないものがあります。どのような薬剤を使うのか確認し、分からないことは主治医や薬剤師に聞いてみましょう。
なお、薬剤は胎児に影響を及ぼすため、治療中は避妊してください。また、治療終了後も薬剤によって一定期間避妊することが勧められています。
| 細胞障害性抗がん薬を使用した場合 | 精子のもととなる細胞は分裂が盛んなため、薬剤の影響を受けやすく、精液の中に精子がない状態(無精子症)になることがあります。治療終了から数年後に精子形成が回復することがあります。 特にアルキル化剤や白金製剤を使用した場合は、精子のもととなる細胞を極度に減らすため、精子形成の回復は難しくなります。使用量が増えるほど精巣へのダメージは大きくなり、精子のもととなる細胞がすべてなくなってしまうことがあります。 |
|---|---|
| 新しい分子標的薬を使用した場合 | 生殖機能や胎児への影響については、まだ十分なデータがありません。 |
| 内分泌療法薬を使用した場合 | 男性ホルモンを抑制するため、性欲低下とともに精子の形成に影響します。 |

2.妊孕性温存療法と生殖補助医療
まずは必要ながんの治療を受けることが大前提ですが、妊孕性を温存できるような治療方法を選択できる場合があります。この治療方法を妊孕性温存療法といいます。
例えば、がんの治療に影響がないか十分に検討した上で、手術の際に勃起や射精に関わる神経を残すことがあります。
そのほかの妊孕性温存療法として、精子の凍結保存を行うこともあります。
パートナーの妊娠を試みる際には、凍結保存していた精子を融解し、顕微鏡下で卵子に注入する顕微授精を行います。顕微授精によって胚(受精卵)になった状態で、パートナーの子宮内に移植し、妊娠を試みます。これを生殖補助医療といいます。精子の凍結保存は、一般の不妊症患者に対する生殖補助医療として、安全性や有効性が確立しており、がん患者に対しても行われるようになってきました。ただし、パートナーの妊娠や出産を約束するものではありません。
以下で「精子凍結保存」についてまとめています。
精子凍結保存
思春期以降では確立された妊孕性温存の方法です。できるだけ、がんの治療開始前に精子を採取し、凍結します。精子の採取はマスターベーションによる精液採取が一般的です。
一方で、がんの治療開始前であっても、もともと精子の数が少ない場合があります。その場合には、通常の方法では精子凍結保存ができない可能性があります。また、思春期前の男児の場合、確立された妊孕性温存の方法はありません。
そのような場合には、精巣内にある精子を採取する方法もあります(精巣内精子採取術)。ただし、精巣内精子採取術が可能な施設は限られているため、男性不妊を専門としている生殖医療専門医に相談する必要があります。
3.妊孕性温存療法・生殖補助医療にかかる費用と助成制度
精子の凍結やその保管、凍結した精子を融解してパートナーの妊娠を試みるための生殖補助医療の費用は、保険適用外で全額自己負担になるため、受診する予定の医療機関に確認しましょう。
ただし、がんの治療によって妊孕性が低下する可能性があると認められた場合は、お住まいの都道府県から妊孕性温存にかかる費用の助成を受けることができます。助成の対象になるかどうか主治医に聞いてみましょう。助成内容・費用は都道府県によって異なる場合がありますので、詳細は関連情報からお住まいの都道府県の情報をご確認ください。なお、助成を受けるのに所得制限はありません。
妊孕性温存療法の助成内容
妊孕性温存療法で助成対象となる治療は表4の通りです。助成を受けるには、対象者が43歳未満であることや、各都道府県が指定した施設で妊孕性温存療法を受けることなどいくつかの条件があります。
助成上限額(2023年6月現在)
| 対象※1 | 対象となる治療 | 助成上限額/1回※2 |
|---|---|---|
| 43歳未満の方 | 精子凍結 | 2万5,000円 |
| 精子凍結 (精巣内精子採取) |
35万円 |
生殖補助医療の助成内容
生殖補助医療を受ける場合に助成対象となる治療は表5の通りです。助成を受けるには、妻の年齢が43歳未満の夫婦であることや、各都道府県が指定した施設で生殖補助医療を受けることなどの条件があります。
助成上限額(2023年6月現在)
| 対象※1 | 対象となる治療 | 助成上限額/1回※2 |
|---|---|---|
| 妻の年齢が 43歳未満の夫婦 |
凍結した精子を用いた 生殖補助医療 |
30万円 |
4.妊孕性温存について相談したいときは
妊孕性温存について検討する際は、まずは主治医に相談しましょう。その上で、必要に応じて生殖医療を専門とする医師(泌尿器科医または産婦人科医)を主治医に紹介してもらい、生殖医療専門医とも相談しながら検討していくことが必要です。主治医に相談しにくい場合は、がん相談支援センターで相談してみましょう。
5.関連リンク
6.参考文献
- 日本癌治療学会.小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年版,金原出版

