1.経過観察
治療後は、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、がんのステージ(病期)や治療法によって異なります。
内視鏡治療を行ったあとは、主に大腸内視鏡を用いた定期検査を受けます。一方、手術を行ったあとは、治療後3年目までは、3カ月ごとの血液検査や6カ月ごとの画像検査(CT検査)を受けます。また、大腸内視鏡検査も定期的に受けます。治療後4年目以降は、6カ月ごとに血液検査と画像検査を受けます。画像検査の間隔は、切除した大腸がんのステージ(病期)によって異なり、6~12カ月ごとです。定期検査が必要な期間の目安は5年間です。
2.日常生活を送る上で
規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙すること、飲酒をひかえること、バランスのよい食事をとること、適度に運動することなどを日常的に心がけることが大切です。
症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調をみながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。
また、患者会や患者サロンなどでは、同じ病気や障害、症状がある、同じ治療を受けたなど、共通の体験をもつ人から、生活などについて情報を聞くことができます。患者会や患者サロンなどの情報は、がん相談支援センターで入手することもできます。
1)内視鏡治療後の日常生活
内視鏡治療は大腸の機能を大きく損なうことがないため、治療後は1週間程度で治療前と同じような生活を送れるようになります。
2)手術(外科治療)後の日常生活
手術後も、ほとんどの場合、治療前と同じような生活を送れるようになります。しかし、そこまで回復するのにかかる時間は、年齢や体力、手術の方法、その他のさまざまな状況により異なります。手術の影響により、排尿や排便などのトラブルが起こることもあります。数カ月たつとある程度は改善するといわれていますので、できる工夫を取り入れていきましょう。
(1)排尿障害について
手術の内容によっては、排尿を調節している自律神経が影響を受けることがあり、尿意を感じない、排尿してもスッキリしない、などの症状があらわれることがあります。また、尿が出せなくなることもあります。時間の経過や薬で改善することが多いですが、導尿(カテーテルという細い管を尿道から膀胱に挿入して尿を採る処置)が必要になることもあります。症状が重い場合や続く場合などには、担当医と相談して、必要に応じて泌尿器科の医師の診察を受けるとよいでしょう。
(2)排便障害について
手術後には、腸を切除した影響や癒着により、排便が不規則になる、下痢や便秘になる、ガスが出にくくなりおなかが張るといった症状がみられることがあります。また、直腸がんの手術後には、1日に何度も便意を感じることがあります。一度排便に行くと数回続く場合や、毎食後に便意をもよおす場合もあります。多くの場合、手術から時間が経つにつれて少しずつ改善してきますが、どの程度まで改善するかには個人差があります。
下痢の症状がある場合は、脱水症状を避けるため、水分を多めにとりましょう。必要に応じて担当医から整腸剤を処方されることもあります。また、ガスが出にくくなりおなかが張ったり、便秘になったりした場合には、おなかを温めたり、マッサージをしたり、水分を十分に摂取したりすることが大切です。必要に応じて担当医から緩下剤(便を軟らかくする薬)を処方されることもあります。排便や排ガスが全くない場合は、腸閉塞の前触れの可能性があります。すぐに担当医に相談しましょう。
(3)運動・外出について
手術後は、1〜3カ月程度で手術前の日常生活が送れるように、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動から始めて、こまめに体を動かすようにしましょう。ただし、腹筋を使う激しい運動は数カ月間控えましょう。自分の体力に合わせて少しずつ行動範囲を広げていくことが大切です。
手術後の排便コントロールが難しい時期に外出する場合には、トイレの場所をあらかじめ確認しておくようにすると、便意を感じたときにあわてずにすみます。下着の中に小さなパッドを敷いておいたり、替えの下着を用意しておいたりすると安心です。
人工肛門(ストーマ)のある人の外出
公共機関やショッピングセンターの施設構内などには多機能トイレがあります。多機能トイレの多くはオストメイト(ストーマをもっている人のこと)に対応しており、シャワーやサニタリーボックス(汚物入れ)、着替え台などが設置されています。オストメイト対応のトイレには、図12のようなマークがあります。外出する際には、事前にオストメイト対応トイレのある施設を探しておくとよいでしょう。
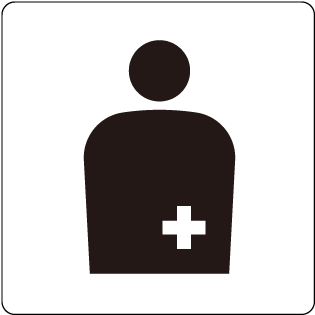
永久的な人工肛門(ストーマ)を造設した場合には、身体障害者の認定の対象となります。認定されると身体障害者手帳が交付され、ストーマ装具費用の給付や公共交通機関の割引、税金の減免などの助成が受けられます。また、条件により障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)を受給できる場合もあります。
申請できる条件や手続きの方法などの詳しい情報は、お住まいの市区町村の福祉関係の窓口でご確認ください。自分が対象者に該当するか、どのように申請したらよいかなどの具体的な疑問について、がん相談支援センターやソーシャルワーカー、市区町村の福祉関係の窓口などに確認することもできます。
(4)手術後の食事について
通常は、退院後に食事の制限はありません。食事はゆっくりよくかんで、そして食べすぎないように腹7〜8分目を心がけましょう。食物繊維の多い食物(わかめ・のりなどの海藻類、ゴボウ・タケノコなどの煮くずれしない野菜など)や消化しにくいもの(揚げ物や中華料理など油の多い食事)は、手術後しばらくは避けましょう。なお、大腸を切除しても、栄養吸収への影響や体重の減少はほとんどないとされています。
3)薬物療法中の日常生活
近年では、新しい薬の登場や支持療法の進歩などにより、通院で薬物療法を行うことが増えています。通院による薬物療法には、自宅での生活を続けながら治療を受けられるメリットがあります。しかし、仕事や家事、育児、介護などを治療前と同じように担うことが難しくなることもあります。予想される副作用やその時期、対処法については、医師や薬剤師、看護師からの事前の説明をよく聞いて確認しておき、特に体調の悪いときには周囲にサポートを求めるなど、自分にできる工夫を探してみましょう。
通院は、疑問や不安に思うことを医療者に伝えるよい機会です。気付いたこと、気になることを日ごろからメモをしておくと役立ちます。また、病院に連絡して受診が必要か確認したほうがよいのはどんなときか、あらかじめ医療者に確認しておきましょう。
4)性生活について
性生活によって、がんの進行に悪影響を与えることはありません。また、性交渉そのものがパートナーに悪い影響を与えることもありません。しかし、がんやがんの治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。がんやがんの治療による性生活への影響や相談先などに関する情報は、関連情報「がんやがんの治療による性生活への影響」をご覧ください。
骨盤内には性機能に関係する神経があるため、男性では、直腸がんの手術後に勃起不全や射精障害などの性機能障害が起こることがあります。女性では、腟の湿潤度などに影響することがあります。
なお、薬物療法中やそのあとは、腟分泌物や精液に薬の成分が含まれることがあるため、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使いましょう。また、薬は胎児に影響を及ぼすため、治療中や治療終了後一定期間は避妊しましょう。経口避妊薬などの特殊なホルモン剤を飲むときは、担当医と相談してください。
家族やパートナーとの関係に加え、治療中の夫婦関係のことなど、男性として、女性としてのつらい気持ちや悩み、心配事が重なることは少なくありません。今の自分の気持ちを落ち着いて整理する、担当医や看護師などの医療者に伝える、自分と似た経験をした人の話を患者会などで聞くといったことが役立つかもしれません。パートナーや家族と一緒に話し合ってみるのもよいでしょう。前向きな気持ちになれない日々が続くのも自然なことと捉えて、あまり否定的になりすぎないことも大切です。
以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。
| 2025年03月24日 | 「大腸癌治療ガイドライン 医師用 2024年版」より内容を更新しました。 |
| 2022年11月10日 | 「大腸癌治療ガイドライン 医師用 2022年版」より、内容を更新しました。 |
| 2020年01月30日 | 「大腸がん治療ガイドライン2019年版」より、内容の更新をしました。 |
| 2018年06月12日 | 「大腸癌治療ガイドライン 2016年版」「大腸癌取扱い規約 第8版(2013年)」より、内容の更新をしました。4タブ形式に変更しました。 |
| 2018年02月21日 | 「大腸がん」のタイトルを「大腸がん(結腸がん・直腸がん)」に変更しました。 |
| 2016年01月06日 | 各項目の内容を治療の種類別に変更しました。 |
| 2013年03月26日 | 内容を更新しました。 |
| 2012年10月26日 | 更新履歴を追加しました。タブ形式に変更しました。 |
| 2011年11月10日 | 内容を更新しました。 |
| 1997年09月22日 | 掲載しました。 |
