1.口内炎・口内の乾燥について
口内炎(口腔粘膜炎)は口の中の粘膜に起こる炎症で、粘膜が赤く腫れたり、痛みが生じたりします。口内の乾燥は口が乾いた状態のことで、ドライマウス(口腔乾燥症)ともいいます。
口内炎や口内の乾燥は、合併症の1つとしてがんの治療中によくみられます。使用する薬剤で起こりやすさは違いますが、がんの薬物療法を受けた約半数の人で起こります。また、頭頸部がん(口、耳、鼻、のどなどのがん)に対する放射線治療を受けたほとんどの人に起こります。例えば唾液の分泌が減って口内が乾燥すると、不快に感じたり、話しにくくなったり、食べものが飲み込みにくくなったりします。また、唾液の持っている口の中をきれいに保つ働き(自浄作用)が低下して細菌などが繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病を含めた感染症のリスクが高まります。さらに、口内炎の強い炎症や痛みは食事や睡眠が十分に取れない原因となり、体力が低下してがんの治療が継続できない状況につながることがあります。
口内炎や口内の乾燥を予防するためには、がんの治療を開始する前に歯科を受診して口腔内の状態をチェックし、必要な治療を受けること、治療前から口腔ケア(歯磨きとうがい)を行うことが大切です。こうした予防対策は、トラブルが起こった場合に症状を軽くすることにもつながります。
また、口内炎や口内の乾燥が起こったときは、すぐに担当医や歯科医師、看護師などに症状を伝え、早めに適切な治療を受けましょう。口腔ケアを継続することも大切です。
2.原因
口内炎の多くは、がんの薬物療法、あるいは頭頸部がんの放射線治療によって、口の中の粘膜が傷つけられたり、唾液を作る細胞がダメージを受けたりすることが原因で起こります。また、歯磨きやうがいが十分にできていないこと、加齢や薬の副作用などで免疫力が低下すること、食事が十分にとれず栄養状態が不良になること、喫煙、入れ歯が合わず粘膜を傷つけてしまうことなども原因となります。
口内の乾燥の多くは、がんの薬物療法や放射線治療、酸素療法(乾燥した酸素の吸入)、薬(医療用麻薬や抗不安薬、睡眠導入剤)の副作用、食事がとれないこと(水分摂取量の低下)などによって、唾液が十分に出なくなることが原因で起こります。
3.口内炎・口内の乾燥が予想されるとき、起こったときは
口内炎や口内の乾燥による痛みや不快感は、食事や会話、睡眠などのクオリティ・オブ・ライフ(生活の質:QOL)に影響を及ぼします。また、放置して悪化すると、体力が低下してがん治療の継続が困難になる可能性もあります。いつもと違う症状などに気がついたら早めに担当医や歯科医師、看護師、薬剤師に相談し、適切に対処しましょう。
1)口内炎
口内炎を防ぐためには、まず口腔内を清潔に保つことが大切です。歯磨きやうがいで口内を清潔にして、栄養バランスの取れた食事を心がけること、十分な睡眠と休養を取ること、ストレスを溜めないようにすること、こまめに水分を補給して口内の乾燥を防ぐことなどが効果的とされています。
口内炎が起こったときには、患部を刺激しないように、歯磨きをやさしく丁寧に行い、熱いものや刺激の強い食べものは避けるようにします。患部からの感染を予防するため、水やうがい薬で口をすすぎ、うるおいと清潔を保ちます。
痛みが強い場合は、医師の判断で、炎症を抑える軟膏(ステロイド、アズレンなど)を塗って緩和したり、必要に応じて痛み止めの薬(鎮痛剤)を使ったりすることがあります。痛みが強く食事ができない場合には、小さな口内炎であっても、うがい薬に局所麻酔薬(リドカインなど)を混ぜて使用することもあります。また、うがいが届きにくい唇の周り(口唇粘膜)などに口内炎ができた場合は、液体の口腔粘膜保護材で保護して痛みを和らげたり、のどの辺りまで口内炎が広がるなど、症状が強い場合には、医療用麻薬を使ったりすることもあります。なお、症状が強くて食べものが飲み込みづらく、誤嚥や肺炎の危険性がある場合には、点滴などによる栄養補給を検討することもあります。
口内炎の発症そのものを防ぐことは難しい面がありますが、適切に症状に対処し、口の中を清潔に保つことによって、口内炎の悪化や感染症を防ぐことが大切です。
薬物療法や放射線治療によって起こる口内炎は、基本的には一時的なもので、治療が終了すれば症状はおさまります。
2)口内の乾燥
口の乾燥を防ぐためには、こまめな水分補給、唾液の分泌を促す食品(梅干し、レモンなど)の摂取、口腔内の保湿ケア(うがいをする、市販の保湿ジェルやスプレーなどの口腔保湿剤を使うなど)、加湿器の利用、そして生活習慣の見直し(カフェイン、アルコールの摂取や喫煙を控える、ストレスを溜めない、よく噛んで食べるなど)が効果的です。ただし、梅干しやレモンなどの酸味の強い食品は、口内炎がある場合に刺激となってしみることがあるため、状況に応じて摂取を控えるなど注意しましょう。
口内の乾燥が起こったときには、すぐに水分を補給し、頻繁にうがいをしたり、市販の口腔保湿剤を使ったりして口の中を湿らせます。また、唾液の分泌を増やすために、ガムを噛むことや、唾液腺(唾液を作るところ:耳の下やあごの下)をマッサージすることが効果的な場合があります(唾液腺刺激療法)。ただし、症状の原因によっては効果が出ないこともあるため、担当医や歯科医師の診断と指導のもとで指示に従って行うようにしてください。唾液腺を刺激して唾液を出す薬(ピロカルピン塩酸塩など)を使用することもあります。
4.本人や周りの人ができる工夫
主なものとして、こまめな口腔ケアや食事の工夫などがあります。
1)口腔ケア
口腔ケアは、治療効果の向上、副作用の軽減、生活の質の維持に欠かせないものです。病気や治療の状態、食事をしたかどうかに関わらず毎日行いましょう。また、自分だけでケアをすることが難しい場合は、医師や歯科医師、看護師、薬剤師などに相談したり、周りの人に手伝ってもらったりすることも大切です。
なお、喫煙や飲酒は口腔粘膜に傷害を与えます。禁煙し、飲酒は控えましょう。
(1)基本的なケア
歯磨き・歯間清掃
毛が柔らかくヘッドの小さい歯ブラシで、1日2~4回、歯や歯茎をやさしくみがきます。通常の歯磨きのあとに、細いブラシ(ワンタフトブラシ)や歯間ブラシを用いてみがくとよいでしょう。舌は専用のブラシ(舌ブラシ)を用いるなど、傷つけないようやさしくみがきましょう。
入れ歯を使用している場合は、毎食後に入れ歯を外し、流水で食べかすなどを洗い流してから、義歯用のブラシ(入れ歯用ブラシ)で丁寧に清掃することが基本です。清掃後は口の中もきれいにします。口をすすぎ、柔らかいブラシ(スポンジブラシなど)を使ってやさしくみがきます。ただし、粘膜がただれている場合は刺激になって痛むことがあるため、無理はせずにうがいなどで清潔を保ちましょう。入れ歯は、必ず専用の洗浄剤で1日1回は洗浄し、夜間は外して清潔にしてから水の入った密閉容器に保管します。入れ歯が合わなくなると、粘膜を傷つけることがあるため、早めに歯科医師に相談しましょう。

うがい・保湿
うがいは口の中のうるおいと清潔を保つのに役立ちます。水または生理食塩水(500mlの水に対して小さじ1杯分の食塩を溶かした食塩水)、あるいはアルコールやヨウ素を含まない刺激の少ないうがい薬を使って行うのがよいでしょう。1日4回以上が目安になります。うがいができない場合は、スポンジブラシをうがい薬にひたし、口の中を拭くことで口内を湿らせます。また、こまめに水分を摂って口の中が乾燥しないようにしたり、市販の口腔保湿剤を使って口の中を潤したりすることも大切です。唇や口角もワセリンなどの保湿剤を使って忘れずに保湿しましょう。
(2)口内炎のときのケア
口内炎のときは、歯磨き剤を使用しない、または低刺激性の歯磨き剤を使って歯磨きをすることがお勧めです。痛みが強いときには、濡れたガーゼでぬぐうか、うがいをするだけにしておきます。
(3)口内の乾燥が気になるときのケア
口内の乾燥が気になるときは、水で濡らしたガーゼで口をぬぐったり、市販の口腔保湿剤を使ったりすることで症状が緩和します。市販の口腔保湿剤には、ジェルタイプやスプレータイプがあります。スプレータイプの保湿剤は口が十分に開けられない場合や外出しているとき、夜間に目が覚めたときなどに便利です。1日数回気がついたときに保湿しましょう。アルコールを含む洗口液でうがいをすることは控えたほうがよいといわれています。
2)食事
十分に食事をとり、体力をつけることが口内炎の治療に役立ちます。口内炎によって口の中が痛い場合には、料理の味付けを酸味やスパイスを控えた薄味にして、できるだけ刺激を少なくします。また、口の中を刺激しないよう、食べものや飲みものは人肌程度に冷まし、食べものは軟らかくしたり、細かく刻んだり、とろみをつけたりします。水分が多いもの、口当たりのよいものを選ぶとよいでしょう。食べられないときは、栄養士に相談しながら、濃厚流動食(バランス栄養飲料)や栄養補助食品なども利用しましょう。
3)周りの人に相談する・本人をサポートする
周りの人に口内炎・口内の乾燥の状態や日常生活の困りごとなどを相談することで、サポートを受けやすくなったり、気持ちが楽になって精神的な負担が軽減されたりすることがあります。また、自身では気づかなかった変化に気がつくきっかけになることもあります。遠慮なく相談することが大切です。
周りの人は、日頃から本人の様子に注意しながら、口腔ケアや食事などの面で手伝えることがないかを確認し、協力するとよいでしょう。本人の気持ちを聞いたり、気分転換になるような声かけをしたりすることで、本人の気持ちが楽になることもあります。また、症状が悪化しても、本人は変化に気づいていなかったり、気づいていても我慢していたりすることもあります。変化に気づいたときは、必要に応じて本人に伝えたり、病院に相談したりしましょう。
5.こんなときは相談しましょう
口の中が痛い、乾燥する、食べものがしみる、飲み込みにくい、入れ歯が合わなくなったなど、いつもと違う症状があると感じたときは、医師や歯科医師、看護師、薬剤師などの医療者に相談しましょう。我慢せず、症状が出始めたときに相談することが大切です。
特に、頭頸部への放射線治療を受けた場合は、唾液腺のダメージなどにより唾液の分泌量が減少し、口の乾燥が長期間(数年以上)にわたって続くことがあります。速やかに医療者に相談し、適切に対処するようにしましょう。
近年、歯科医師や歯科衛生士による専門的な口腔ケアも推奨されています。歯科治療を受けるときは、まずがんの治療の担当医にその旨を伝え、歯科医師にはがん治療の状況を詳しく伝えることが大切です。
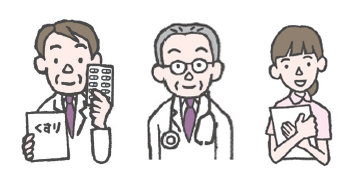
6.関連情報
7.参考資料
- 国立がん研究センター内科レジデント編.がん診療レジデントマニュアル 第9版.2022年,医学書院
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構ウェブサイト.重篤副作用疾患別対応マニュアル(医療関係者向け)抗がん剤による口内炎;2023年(閲覧日2025年8月14日)https://www.pmda.go.jp/index.html
- 日本がんサポーティブケア学会ウェブサイト.刊行物・ガイドライン「JASCCがん支持医療ガイド翻訳シリーズ」口腔ケアガイダンス 第1版日本語版;2018年(閲覧日2025年8月14日)http://jascc.jp/
- 日本口腔ケア学会学術委員会編.口腔ケアガイド.2012年,文光堂
- 上野尚雄ほか編.がん患者の口腔マネージメントテキスト―看護師がお口のことで困ったら―.2016年,文光堂
- がん情報サービス医療関係者向け情報ウェブサイト.在宅療養中のがん患者さんを支える口腔ケア実践マニュアル;2013年(閲覧日2025年8月14日)https://ganjoho.jp/med_pro/index.html
- 森田達也ほか監修.緩和ケアレジデントマニュアル 第2版.2022年,医学書院
- 日本がんサポーティブケア学会/日本がん口腔支持療法学会編.JASCCがん支持医療ガイドシリーズ がん治療に伴う粘膜障害マネジメントの手引き 2020年版.2020年,金原出版.
- Saunders DP, et al. Systematic review of antimicrobials, mucosal coating agents, anesthetics, and analgesics for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines. Support Care Cancer. 2020; Volume 28: 2473–2484.
- Peterson DE, et al. Management of oral and gastrointestinal mucosal injury: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment, and follow-up. Ann Oncol. 2015; Volume 26(Suppl 5): v139–v151.
- Hong C, et al. MASCC/ISOO Clinical Practice Statement: Management of salivary gland hypofunction and xerostomia in cancer patients. Support Care Cancer. 2024; Volume 32, https://doi.org/10.1007/s00520-024-08688-9.
※本ページの情報は、「『がん情報サービス』編集方針」に従って作成しています。十分な科学的根拠に基づく参考資料がない場合でも、有用性が高く、身体への悪影響がないと考えられる情報は、専門家やがん情報サービス編集委員会が評価を行ったうえで記載しています。
作成協力
