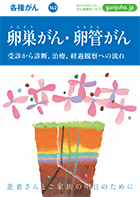卵巣がんは卵巣に、卵管がんは卵管に発生する悪性腫瘍です。
がんが初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。服のウエストがきつくなる、下腹部にしこりが触れる、食欲がなくなったなどの症状をきっかけに受診し、卵巣がん・卵管がんであることがわかる場合もあります。また、がんが大きくなると、膀胱や直腸を圧迫することにより、頻尿や便秘が起きたり、脚がむくんだりすることもあります。進行して腹水がたまると、おなかが大きく前に突き出てくることもあります。
がんの診断から治療までの流れなどについては「関連する情報」をご覧ください。
関連する情報
-
卵巣がん・卵管がんについて
卵巣は、子宮の両脇に1つずつある親指大の楕円形の臓器で、骨盤内の深いところにあります。卵巣は、卵巣の… -
検査
卵巣がん・卵管がんが疑われた場合には、腹部の触診や内診のほか、超音波(エコー)検査やCT検査、MRI… -
治療
卵巣がん・卵管がんの治療では、主に手術によりできるだけがんを取り除きます。多くの場合、手術の後に薬物… -
療養
症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なります。体調をみながら、担当医とよく相談して無理のない… -
臨床試験
国内で行われている臨床試験が検索できます。 -
患者数(がん統計)
患者数と生存率の情報です。 -
予防・検診
発生要因と予防と検診の情報です。 -
関連リンク・参考資料
がん診療連携拠点病院などのがんの診療を行う病院やがん相談支援センターを探すことができます。
関連する情報
がんの治療を始めるにあたって、参考となる情報です。
これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。
がんの診療の流れやセカンドオピニオンなどに関する情報を掲載しています。
ご家族や身近な人ががんと診断された人に向けた情報を紹介しています。