1.検査の目的
CT(Computed Tomography、コンピューター断層撮影)検査は、治療前にがんの有無や広がり、他の臓器への転移がないかを調べる、治療の効果を判定する、治療後の再発がないかを確認するなど、さまざまな目的で行われる精密検査です。
2.検査の方法
CT検査は、X線を使って行います。
いろいろな方向から体にX線をあてて、水分、骨、脂肪、空気など体の中にある成分によるX線の吸収率の違いをコンピューターで処理し、体の断面を画像にします。連続した断面の画像を作成することにより、体の中の様子を立体的に把握できます。検査の目的によっては、造影剤を使用する場合があります。
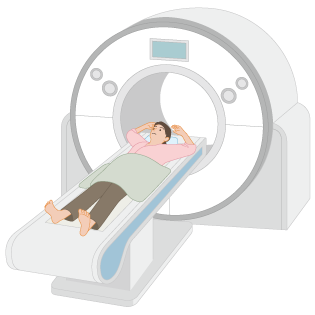
3.検査の実際
CT検査は、ベッドの上にあおむけになった姿勢で行います。検査の際はベッドが自動で動き、トンネル状の装置の中に入ります。撮影部位によっては、体の向きを変えたり、一時的に息を止めたりすることがあります。検査全体にかかる時間は10~15分程度です。
撮影する範囲に眼鏡やベルトなどがあると画像に映り込むため、外せるものは必要に応じて外します。人工関節など外から見て分からない人工物が体内にある場合は、撮影に影響がないか医師に確認しましょう。また、ペースメーカーや除細動器などが体内にある場合は、それらの動作に影響することがあるため、事前の確認が必要です。必ず医師に伝えましょう。
造影剤を使用する場合には、検査を受ける数時間前から食事はできません。造影剤を静脈から注射したときに体が熱いと感じることがありますが、一時的なものですので心配ありません。造影剤は尿によって排せつされるため、検査の後には水分を多めにとりましょう。
造影剤の副作用として、吐き気やかゆみ、くしゃみ、発疹などの症状が100人に数人程度、また、血圧低下、呼吸低下などのショック症状が1000人に1人未満で起こることがあります。これまでに造影剤による副作用の症状が出たことのある人、ぜんそくやアレルギーがある人、糖尿病の薬を飲んでいる人、腎機能が悪い人、授乳中の人は、造影剤の使用に注意が必要な場合がありますので、必ず医師に伝えてください。
※詳しくは、実際に検査を受ける病院で確認しましょう。
4.検査の特徴
CT検査は、10~15分程度の時間で、広い範囲を詳細に撮影できる検査です。体の中の様子を立体的に把握できるため、がんの形や広がりがより詳しく分かります。
CT検査の1回あたりの放射線被ばく量は、X線検査より多くなります。検査による被ばくの影響を過度に心配する必要はありませんが、胎児は放射線の影響を受けやすいため、妊娠している人、妊娠している可能性がある人は、必ず医師に伝えてください。
5.CT検査を行う主ながん
CT検査は、がんの診断において最も基本となる画像検査で、血液のがんも含めて、ほぼすべてのがんで行うことがあります。
(50音順)
6.Q&A
-
Q1CT検査による被ばくが心配です。体への影響はありませんか?何回撮っても大丈夫なのでしょうか?
A1通常、人の健康に影響することが確認されている放射線の1回量は100mSv以上です。一方、1回のCT検査で被ばくする放射線量は、検査する臓器や範囲によってかわりますが、おおむね5~30mSvです。放射線量は、患者の年齢や体格などに合わせて調整されています。また、CT検査によって被ばくしダメージを受けた細胞のほとんどは、そのたびに修復されて正常な細胞に戻ります。
※Svとは、放射線が人間にあたったときにどれだけ健康に影響があるかを評価するために使う単位です。
このことから、複数回検査を受けたとしても、検査による被ばくの影響を過度に心配する必要はありません。また、検査を行うのは、被ばくの影響よりも、がんを発見したり、がんの広がりや治療の効果を確認したりするなど、現在の体の状態を調べるメリットの方が大きい場合だけです。
不安がある場合は気になる点を医師に伝えて説明を受けましょう。なお、胎児は放射線の影響を受けやすいため、妊娠している人、妊娠している可能性がある人は、必ず医師に伝えてください。
放射線検査による被ばくと健康への影響、放射線検査を受ける意義などについて解説されています。
作成協力
